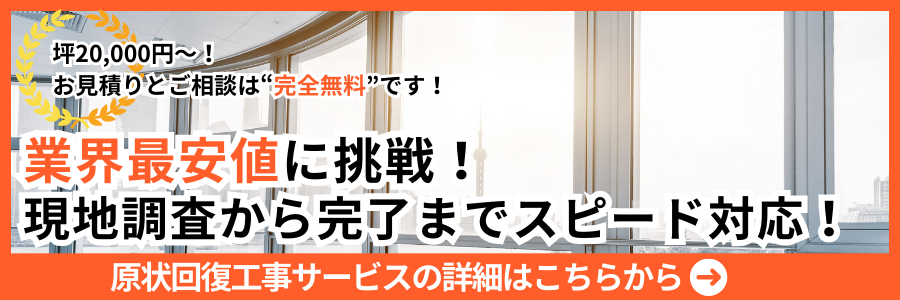原状回復工事とは?工事の内容や流れ・費用相場・安くする方法を解説
オフィスを移転する際には、原状回復工事の実施が必要です。
しかし原状回復工事とはどんな工事で、どんな流れで進めるべきかわからず悩んでいる方もいるでしょう。
そこで本記事では、原状回復工事がどんな工事なのか、概要や流れを解説します。
費用相場・安くする方法についても解説するので、原状回復工事を予定している方は参考にしてください。
目次

・1.原状回復工事とは?
・1.1.原状回復工事は入居前の状態に戻す工事
・1.2.原状回復と現状回復の違いは?
・1.3.原状回復と現状復帰の違いは?
・2.原状回復工事は一般的に誰が負担する?
・2.1.A工事は業者選び・発注・費用までオーナーが負担する
・2.2.B工事は業者選びをオーナー、発注・費用は入居者が負担する
・2.3.C工事は業者選び・発注・費用まで入居者が負担する
・3.原状回復工事の具体的な工事内容とは?
・3.1.間仕切りや造作物の撤去や解体
・3.2.天井・壁・建具・枠周りの塗装
・3.3.壁紙やタイルカーペットの張り替え
・3.4.防災設備や空調機器を元の位置に戻す天井設備関連工事
・3.5.床下の配線やOAタップの撤去・照明器具の交換といった電気関連工事
・3.6.什器や備品の撤去
・3.7.産業廃棄物の処理
・3.8.窓や照明器具のクリーニング作業
・4.原状回復工事の工事区分とそれぞれの注意点
・4.1.A工事
・4.2.B工事
・4.3.C工事
・5.原状回復工事を行う流れ
・5.1.①賃貸借契約書をチェック
・5.2.②施工業者と打ち合わせ・現地調査
・5.3.③契約を結び発注・着工
・8.原状回復工事を安くする方法はある?
・8.1.費用が高くなる時期を避けて工事を依頼する
・8.2.C工事に変更できるかオーナーに確認する
・8.3.業者の見積もり内容を見直す
・8.4.複数の業者に見積もりを依頼する
・9.原状回復を手掛けた実績・事例
・9.1.新大阪丸ビルの原状回復工事(大阪府大阪市東淀川区)
・9.2.パーソナルジムの解体工事(大阪府高槻市)
・9.3.R&Hビルの原状回復工事(東京都渋谷区)
原状回復工事とは?
原状回復工事とはどんな工事なのか、詳しく解説します。
混同されやすい現状回復・現状復帰との違いも紹介するので、しっかり意味を把握しましょう。
原状回復工事は入居前の状態に戻す工事
原状回復工事とは、賃貸契約が終了する前に、借りていた物件を入居前の状態に戻す工事です。
国土交通省のガイドラインで基準が定められており、細かい工事内容は契約内容によって異なります。
借主によって賃貸の使い方は異なるため、次の借主も使いやすい部屋の状態に戻す必要があることが、原状回復工事を施工する理由です。
新築と変わらない状態に戻すのは難しいので、配置を変更した空調や照明・設置したパーテーションなどの撤去を行い、入居前の状態に戻します。
原状回復と現状回復の違いは?
現状回復とは、原状回復の誤った表記方法です。現状とは現在の状況を指すので、現状回復と書くと「現在の状態に回復する」という意味になります。賃貸借契約において適切な言葉とは言えないので、誤った表現です。
見積書など書類で「現状回復」と表記されている場合もありますが、漢字の誤りです。正しい表記は「原状回復」なので、記入するときは気をつけましょう。
原状回復と現状復帰の違いは?
現状復帰とは、元の状態に戻す行為を指す言葉です。
元の状態に戻す「原状回復」とほとんど同じ意味を持ちますが、主に使われる場面が異なります。原状復帰は建設業関係者・建設業界で使われることが多い言葉で、原状回復は法律用語・賃貸借契約書などの契約に関する場面で使われる言葉です。
またオフィス移転の際に使われることが多い原状回復に対して、「現状復帰」は災害時に損傷を受けた建物や住宅設備を被災前の状態に戻すときに使われます。
原状回復工事は一般的に誰が負担する?

工事内容によって負担者が異なりますが、原状回復工事はすべてB工事というビルが多いです。
誰が工事を負担するのか定めた工事区分について、確認しましょう。
A工事は業者選び・発注・費用までオーナーが負担する
A工事は共用部分や建物の基礎・骨組みに関する工事を指し、業者選び・発注・支払いまで建物のオーナーが負担します。
一般的には、エントランスや共用エリアのトイレ、エレベーター、給排水やガスのメーター、建物の外壁や屋上などが含まれるケースが多いです。
基本的に借主には、A工事を負担する必要がありません。ただし借主が破損した場合は、修繕費用を請求されることもあるので気をつけましょう。
B工事は業者選びをオーナー、発注・費用は入居者が負担する
B工事は、建物の構造・安全性に関わる部分について、借主の要望により入居時に変更があった部分を元に戻す工事です。
希望を出すのが借主なので、発注・支払いは入居者が負担しますが、業者はオーナーが選びます。
B工事を施工するのは、給排水管・配電盤・防災設備・テナントの壁や天井・照明器具・空調設備などが一例です。
B工事では、A工事の部分も見積もりに含まれてしまうトラブルが多くあります。
本来の予算を超えた金額を請求される可能性があるので、事前に契約内容をチェックし、発注内容に問題がないか確認することが大切です。
C工事は業者選び・発注・費用まで入居者が負担する
C工事は内装工事など、建物自体に影響を及ぼさない借主が行った工事をC工事といいます。
所有権が借主にあるので、業者選び・発注・支払いまですべて借主が決められる点が大きな特徴です。工事内容にはインターネットの配線や電話線の撤去・壁紙や床の張り替え・什器や造作の撤去などが含まれます。
オーナーには工事の確認を取るだけでいいので、費用や工期などは業者と柔軟に交渉できます。ただしC工事でも、オーナーが負担するA工事の内容を請求されてしまうトラブルが発生する恐れがあるため、注意しましょう。
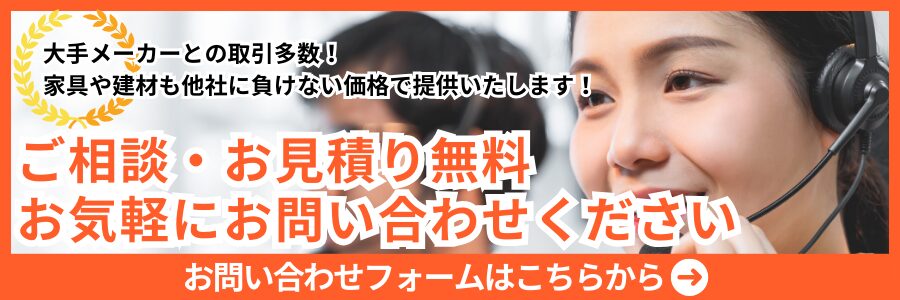
原状回復工事の具体的な工事内容とは?

原状回復工事の一般的な工事内容について、具体的に解説します。どんな工事を施工する必要があるのか、確認しましょう。
間仕切りや造作物の撤去や解体
借主が入居時に設置した、パーテーションやLGSといった間仕切りや造作物の撤去・解体は原状回復工事に含まれます。
騒音が出る作業があるので、管理会社やオーナーによっては解体日・時間を制限していることもあり注意が必要です。
造作を撤去せず、次の借主へ譲渡する「造作譲渡」が可能な物件であれば、施工しなくてもいい場合があります。
天井・壁・建具・枠周りの塗装
塗装は、天井・壁・建具・枠周りなどが範囲に含まれます。状態がよければ塗装せず、清掃のみの対応で問題ないこともありますが、あまり多くはないです。タバコのヤニなどで状態が悪ければ、1度の塗装では仕上げられず2〜3回塗る場合もあります。
塗装時は、臭いに関するトラブルが発生しやすいです。臭いが少ない塗料を活用したり、人のいない時間に進めたりするなど工夫しましょう。
壁紙やタイルカーペットの張り替え
壁紙やタイルカーペットの張り替えや下地ボードの取り替えなどは、オフィスビルでは、全て借主負担が一般的です。
また雨漏りによるシミ・腐食はオーナー負担ですが、雨漏りについてオーナーや管理会社に報告せずにシミ・腐食が発生した場合は借主負担になるので注意しましょう。
防災設備や空調機器を元の位置に戻す天井設備関連工事
原状回復工事には、防災設備や空調機器を元の位置に戻す天井設備に関する工事も含まれます。
間仕切りを設置する際に天井設備を移動・増設した場合は、元の位置に戻すことも必要です。
ただし消防法の改正により、入居時と同じ消防設備を設置できないこともあります。所轄の消防署に確認してから、法令に準じた設備を設置しましょう。
床下の配線やOAタップの撤去・照明器具の交換といった電気関連工事
床下の電話線やLAN線の撤去、照明器具の交換などの電気関連工事も原状回復工事に該当します。
OAタップ、OAフロアを導入しているケースでは、それぞれ撤去工事も施工します。
建物に関わる配線の工事を行う際は、C工事ではなくB工事になる場合もあるので、事前にオーナーへ確認しましょう。
什器や備品の撤去
原状回復工事では、入居後に持ち込んだキャビネットやデスクといった什器・パソコンや複合機といった備品も撤去する必要があります。処分しなければ移転先でも活用できるので、購入費用を抑えられるでしょう。
物件によっては、次の借主へ譲渡できる場合もあります。自前の設備を売却できれば、退去時の費用節約にもつながります。
産業廃棄物の処理
原状回復工事で発生した産業廃棄物の処理も、業者に依頼しましょう。
内装の解体工事を行うと、金属やガラスのくず、瓦礫類、プラスチック類などの産業廃棄物が発生します。
基本的には、原状回復工事を施工する企業に、産業廃棄物の処理もセットで依頼できるケースが多いです。
ただし一括で依頼できない場合は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
窓や照明器具のクリーニング作業
原状回復工事の最後は、クリーニング作業です。
家具の下・窓・サッシ・ブラインド・照明器具・エアコンなどは意外と汚れやすいので、クリーニングを行います。
また水垢やカビが発生しやすいトイレ・給湯室などの水回りも、クリーニングが必要です。
原状回復工事の工事区分とそれぞれの注意点
工事区分は、通常「施工会社の選定や工事費用の負担を誰が行うか」といった事項が取り決められ、これは主に賃貸借契約書に詳細が明記されています。賃貸借契約書によると、工事区分はビルごとに異なる規定があり、一般的には業者の選定と費用負担の差異によってA工事、B工事、C工事の三つに区分されます。
ビルの工事区分表には、具体的にどの工事がどの区分に分類されるのかが記載されていますので、入居前に事前に確認しておくことが重要です。
A工事
A工事は、通常、建物のオーナーが発注し、工事費用も負担します。対象範囲には主に、ビルの外壁、屋上、エレベーター、トイレなどやエントランスなどのビル共用部の修繕が一般的です。
一般的には、ビル全体の躯体工事や共用施設、ガスや給排水のメーターなど、テナント入居者とは直接関係のない工事が含まれることが多いです。A工事の内容は、建物全体のメンテナンスや修繕に焦点を当てています。
B工事
B工事は、通常、建物のオーナーが発注し、入居者が費用を負担します。対象範囲には主に、空調や照明、防災設備、給排水管などの建物全体に関連する設備が多く含まれます。
主に、入居者の要望に基づいてビル全体に変更を加える場合がB工事の区分になります。また、原状回復工事もその大半はB工事に分類されます。
C工事
C工事は、入居者が施工会社の選定や工事費用の負担を行う工事を指します。対象範囲には主に什器やLAN線、電話線などの配線工事、内装工事がC工事に該当します。
オーナーを経由せずに工事業者と直接連絡が取れ、これによりスムーズなコミュニケーションが可能となり、費用や工期に柔軟性が生まれます。
原状回復工事を行う流れ

施工前から完工までの原状回復工事を行う流れについて、詳しく解説します。
工事の流れを把握してから、工事日程を検討しましょう。
①賃貸借契約書をチェック
賃貸借契約書に原状回復工事を行う範囲・工事できる時間や曜日が書かれているため、自分の負担範囲や工事できる日程をチェックしましょう。工事内容や工事する場所によっては、周囲に影響が出ます。賃貸借契約書に工事日程について記載されていない場合でも、管理会社に工事可能な時間や曜日を確認しておくとスムーズです。
マンション・アパートなどの住居であれば賃貸契約が終了してから、オフィス・店舗などテナントの場合は賃貸契約が終了する前に原状回復工事を行います。そのため賃貸契約の終了時期についても賃貸借契約書で確認し、工事を行うスケジュールを検討しておくとよいでしょう。
②施工業者と打ち合わせ・現地調査
賃貸契約書をチェックしたら、施工業者に問い合わせをし、打ち合わせや現地調査を行いましょう。物件や工事内容によっては施工業者が指定されているので、注意してください。C工事で指定の施工業者がない場合は、自社で業者を選びましょう。
問い合わせ後は担当者が立ち会って現地調査を行い、現場や原状回復工事の範囲を確認します。見積もりを依頼し、問題がなければ工事期間やスケジュールを決めます。
③契約を結び発注・着工
見積内容・工事期間に問題がなければ、B工事・C工事のどちらも契約を結び発注します。トラブルを回避するためには、着工後に定期的に進捗を確認したり報告を依頼したりすることがおすすめです。中間検査を実施できる業者は多いので、依頼した方が安心できます。
問題なく完工したら、オーナーにテナントを引き渡しましょう。オーナーの確認時に一緒に確認した方が、認識の違いを防げます。また追加工事を求められる場合もあるので、念のため施工業者と簡単に話し合っておくとよいでしょう。
原状回復工事にかかる期間
原状回復工事にかかる期間は、100坪未満のテナントであれば2週間から1ヶ月程度、100坪以上のテナントであれば1ヶ月前後です。
工事内容が少なければ、1週間程度で終わる場合もあります。
あくまで目安なので、現地の状況や工事内容次第で期間は大きく変わります。
大きな音や臭いの発生する工事などはオーナーから施工日時を指定されることもあるので、2ヶ月前までに問い合わせをするとよいでしょう。
原状回復工事の費用相場

原状回復工事にかかる費用相場は、テナントの広さや工事内容によって異なります。
小規模テナントであれば1坪あたり2~4万円程度、20〜100坪程度なら1坪あたり3〜6万円程度、100坪以上であれば5〜10万円程度かかるのが一般的です。
ただし水回りを大きく変更していたり、暖炉など特殊な内装工事をしていたりすると、費用は高くなります。
また資材費用は日々変動するため、施工時期によって費用が高くなることもあります。
現地調査次第で費用は大きく変わるので、具体的な費用を知りたい場合は見積を依頼しましょう。
原状回復工事を安くする方法はある?
原状回復工事をする際、できる限り安くしたいのが本音でしょう。
費用を安くする方法について紹介するので、ぜひ参考にしてください。
費用が高くなる時期を避けて工事を依頼する
原状回復工事は施工時期によって、費用は異なります。たとえば新年度・決算期など、企業やオフィスの移転が増える時期は施工業者に依頼が増え、費用相場も高くなりやすいです。
またゴールデンウィークやシルバーウィークといった、長期休みのタイミングも業者の予定を押さえにくくなります。
できる限り他社の移転が増える時期や長期休暇を避けて工事を依頼した方が、安く抑えられる可能性があるでしょう。
C工事に変更できるかオーナーに確認する
B工事の内容をC工事に変更できるか、オーナーに確認することも原状回復工事の費用節約に効果的です。
B工事のままだとオーナーが業者を選ぶため、相場より高い金額を支払う可能性があります。
C工事にできれば自分で業者を選定できるので、より費用が安い業者を選んだり、臨機応変に行工事内容について交渉できるでしょう。
業者の見積もり内容を見直す
C工事では、業者の見積もり内容を見直すことで費用を安く抑えられる場合があります。初回は高めの見積もりを出す企業も多いので、適正価格か確認することが大切です。高いと感じた項目があれば指摘し、再度見積もりを依頼しましょう。
また本来は借主が負担しなくていい工事が見積もりには含まれている場合もあります。
工事区分や施工範囲が合っているか、チェックしましょう。
複数の業者に見積もりを依頼する
C工事では、複数の業者に見積もりを依頼する相見積もりを実施しましょう。
相見積もりをすることで、適切な費用相場がわかります。工事区分・工事内容は項目ごとに分けて見積もりを依頼すると、細かい費用をチェックできます。
作業人数・工事面積を出してもらい、余分な人件費がないか、正しい工事面積で見積もりができているか確認しましょう。
また相見積もりで取得した他社の見積もりを提出することで、別の業者が価格交渉に応じてくれることもあります。
複数の業者を見比べられる相見積もりなら、より信頼できる業者が見つかるでしょう。
原状回復を手掛けた実績・事例
弊社が過去に手掛けた原状回復施工事例の一部をご紹介いたします。
1.新大阪丸ビルの原状回復工事(大阪府大阪市東淀川区)
テナント様の要望に応じて、解体、電気設備の改修、内装のリニューアル、雑工事などを行い、最後に美装を施しました。オフィスビルごとに異なる工事内容があるため、安価な見積もりには注意が必要です。当社では綿密な打ち合わせのもと、お客様のご要望にお応えし、最高のサービスを提供することを心がけております。
(新大阪丸ビル原状回復工事の施工事例はこちら)
2.パーソナルジムの解体工事(大阪府高槻市)
以前にもお客様から原状回復工事発注を受けた経緯から、商店街の夜間解体工事やジムの機器・設備撤去を迅速に対応しました。現地調査からわずか2週間後に着工と短工期でしたが、無事完工し、お客様にご満足いただけたことをうれしく思います。
(パーソナルジム解体工事の施工事例はこちら)
3.R&Hビルの原状回復工事(東京都渋谷区)
タイルカーペットの交換や天井・壁への塗装、美装を実施しました。内装は清潔で魅力的な状態に戻り、これにより新しいテナント様とって快適な作業環境を提供でき、ビルオーナー様にとっても資産価値向上に貢献できたことを大変うれしく思います。
(R&Hビル原状回復工事(東京都渋谷区)の施工事例はこちら)
まとめ
原状回復工事とは、賃貸契約の終了前までに、借りていた物件を入居前の状態に戻す工事を指します。
工事範囲は契約内容によって異なりますが、基本的に借主の希望で変更した部分のB工事の支払いと、借主が行った工事のC工事の業者選定から支払いまでが借主の負担です。
原状回復工事の費用を安くするためには、費用が高くなる時期を避けたり、相見積もりをしたうえで見積もり内容を見直したりすることが大切です。これから原状回復工事を予定している人は、本記事を参考に工事の計画を立ててください。
原状回復工事に関するご依頼は「ビルディングデザイン」がおすすめです。年間60~80件の原状回復工事を請け負っています。
営業から現場管理まで自社スタッフで実施するため、大手の管理会社の下請けとしても多数の原状回復工事をしている実績からもオーナーへの信用力も高く金額も低価格で実施しております。管理会社やオーナーとのやりとりも一緒に致しますので安心してお任せ頂けます。
また移転先のオフィスのデザインなどもできるので同時依頼することで更にコストを抑えることもできます。
「ビルディングデザイン」を利用して、費用を安く抑えつつ快適な新オフィスをデザインしませんか。
(ビルディングデザインが手掛ける原状回復サービスの詳細はこちら)